「明日晴れてほしいなあ」
そんなとき、思い出すのがてるてる坊主のおまじない。
「てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ」
子供のとき、歌をうたいながら、てるてる坊主をつるした経験がある方も多いでしょう。
日本人に長く愛されてきたてるてる坊主ですが、どうして彼は晴れをもたらしてくれるのか、ご存知ですか?
また、どういう由来であんな姿をしているのでしょうか?
今回はてるてる坊主についての豆知識や、その由来、作り方や正しい吊るし方などをまとめました。
てるてる坊主の豆知識は?
てるてる坊主って、子供のときに作ることが多いせいか、なんとなくいつの間にか知っていて、なんとなく作っている感じがしませんか?
ここでは、ちょっと興味深い、てるてる坊主にまつわる豆知識をご紹介します。
時代や地方で名前が違う
てるてる法師、照り照り坊主、てれてれ坊主、てれてれぼうし、てらてら坊、てろてろ坊主、日和坊主、てりてり、てり雛などなど。
てるてる坊主には、かつてはいろんな別名がありました。
近代から明治にかけては、てりてり坊主という名前が優勢になった時期でした。
そのため明治期の国語辞典には、「てりてり坊主」という名前で載っている事が圧倒的に多かったそうです。
その後てるてる坊主という名称が広まったのは、童謡がきっかけでした。
あの有名な童謡「てるてる坊主」が発表され、全国的に広く親しまれるようになったのです。
そういったきっかけがあり、てるてる坊主の名称が全国的なものになっていたようです。
てるてる坊主は昔は着物を着ていた
てるてる坊主、江戸時代は着物を着せられた、白い紙人形の姿が一般的だったようです。
着物は和紙を縫い合わせ、帯の部分はこよりを使って手作りされていました。
着物には願掛けの言葉を筆で書き付けて祈ったとか。
今よりもかなり手間ひまかけて作るものだったんですね。
てるてる坊主に似た妖怪がいる
晴天時に山の切り立った崖に現れる「日和坊(ひよりぼう)」という妖怪がいます。
常陸国(現在の茨城県の辺り)に言い伝えられている妖怪です。
晴れをもたらすと言われていて、てるてる坊主と関係があるとも言われています。
てるてる坊主の由来は?
てるてる坊主は中国の風習に由来しているという説があります。
なかなかドラマティックな変貌ぶりですよ。
美しい娘が晴れをもたらした
てるてる坊主の原型は、中国の「掃晴娘(サオチンニャン)」という風習だと言われています。
昔、中国のとある場所に晴娘という美しい娘がいたそうです。
その頃、雨が降り続いて水害が起こり、村人たちはとても困っていました。
晴娘が雨が止むよう天へ祈りを捧げたところ、空の上から龍神の声が響き渡りました。
晴娘が龍神の妃となるなら、雨が止むだろう、と。
優しい晴娘がそれを承諾すると、晴娘の姿は消え去ります。
そして、雨は止み、空は晴れ渡ったのだそうです。
その後、中国では掃晴娘というほうきを持った女の子の紙人形を、晴れ祈願のためにつるすそうになったのだそうです。
ほうきで空の雲を掃き集め、雨が降らないようにしてくれると言われています。
てるてる坊主、男性になる
その風習が、やがて日本に伝わりました。
中国の掃晴娘は女性でしたが、日本では祈願や祈祷は修験者や僧侶など男がするものだったことから、次第に男性の人形となっていったようです。
現代の中国では掃晴娘の風習はなくなりつつあり、知らない人も多いそうです。
もともと由来となった風習は廃れてしまい、後で習った日本では形を変えて残っている。
なんだか不思議な感じがします。
てるてる坊主の作り方や吊るし方は?
てるてる坊主はおうちで簡単に作ることができます。
出来上がったてるてる坊主は正しい方法でつるして、効果をアップさせましょう。
てるてる坊主の簡単な作り方
てるてる坊主を作ったことがありますか?
作り方の基本としては、白い布(ガーゼやハンカチなど)のまんなかに丸めた布や紙を置いて包み、そのまわりをぐるぐる紐で巻いてしばれば完成です。
白い布の代わりにティッシュペーパーでも大丈夫です。
アレンジの効いたかわいいてるてる坊主を作りたい場合は、プリント柄の布や模様付きのペーパーナプキンでも素敵ですね。
てるてる坊主の正しいつるし方は?
ニコニコフェイスのてるてる坊主はかわいらしいですが、おまじないとしては顔を描かずにつるすのが正しい方法です。
のっぺらぼうのてるてる坊主に晴れのお願いをしてからつるします。
そして念願かなって晴れたら、感謝を込めて、目鼻を入れてから処分します。
もし晴れなかったら?
お願いが届かず雨が降ってしまったら、顔を描かずに処分しましょう。
つるす場所は、家の中でなるべく太陽に近い場所、南向きの窓際が良いとされています。
逆さにつるす場合もある?
てるてる坊主を逆さにつるすと、逆さ坊主と言って雨を降らせるおまじないになるのだそうです。
開催されてほしくない行事やイベントだって、人生にはたまにありますしね。
そんなときにも、てるてる坊主が願いをかなえてくれます。
作り方は、てるてる坊主の頭部に重りを入れて、頭が下を向くように作ります。
逆さ坊主のことを、ふれふれ坊主、あめあめ坊主、るてるて坊主などと呼ぶ地方もあるそうです。
まとめ
てるてる坊主には長い歴史があり、その中で姿も呼ばれ方も、さまざまに変化してきたことが分かりました。
これからも、時代に合わせてその姿を変えていくのかもしれませんね。

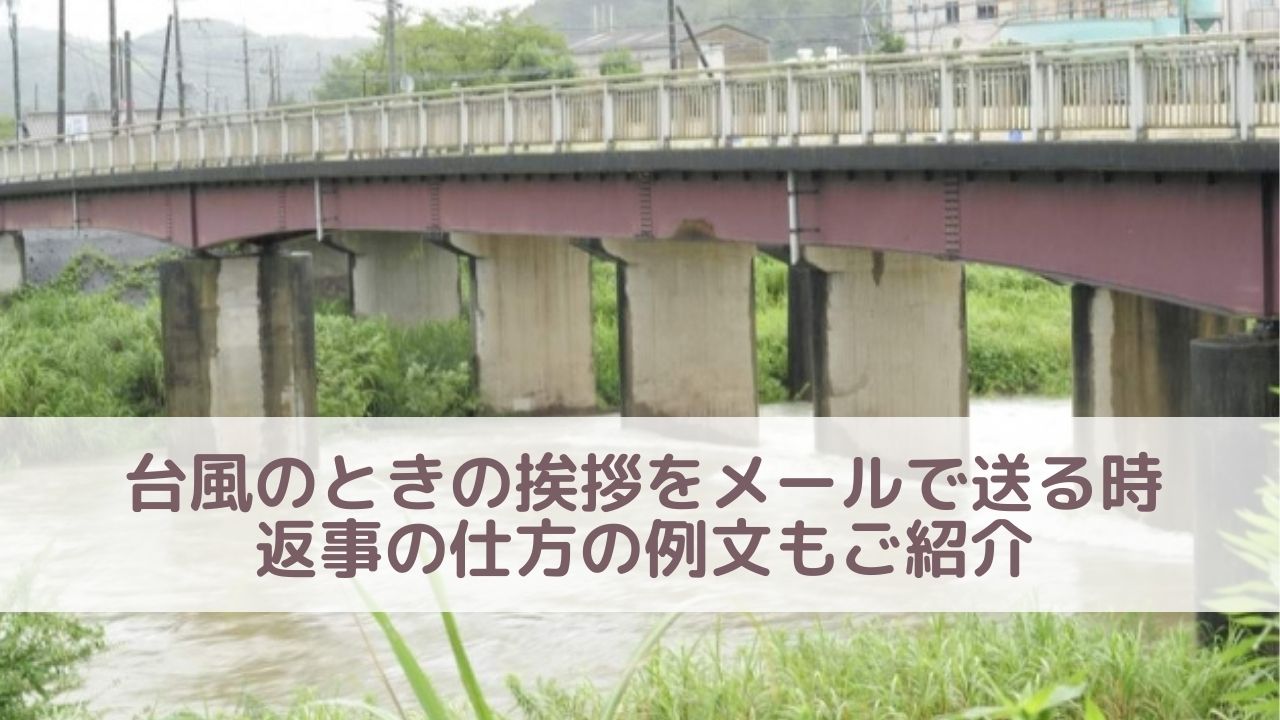








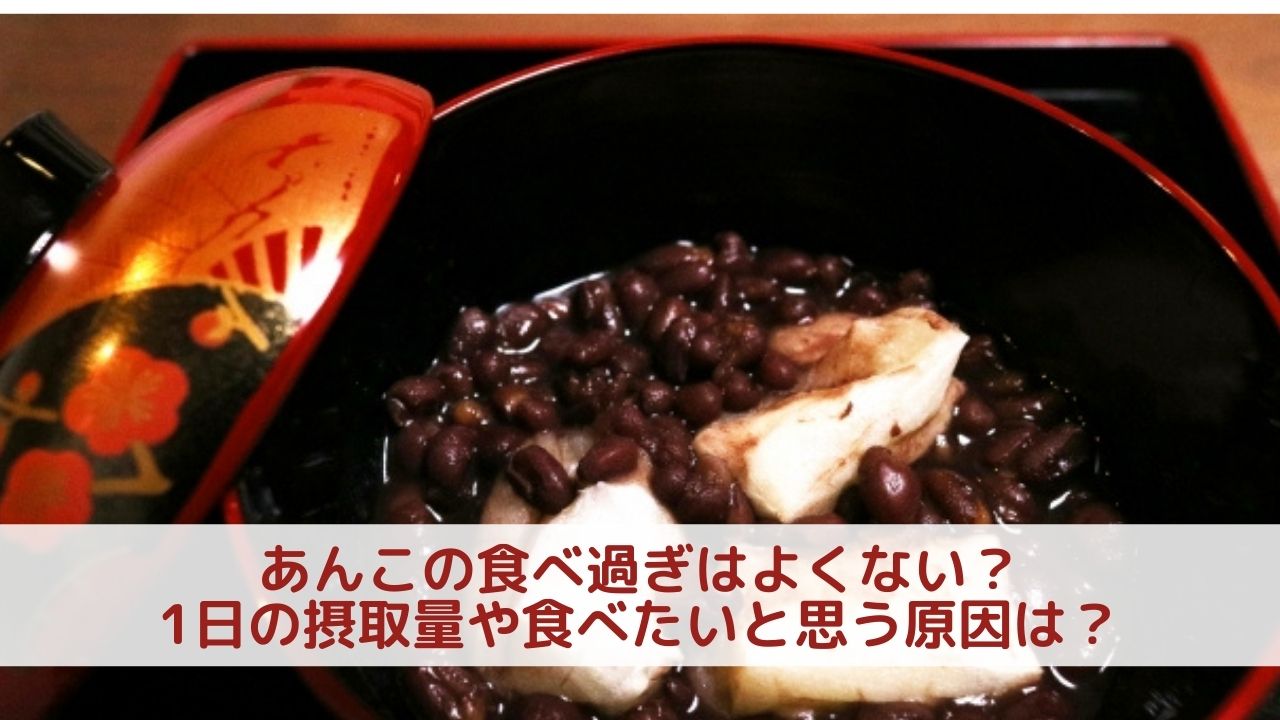



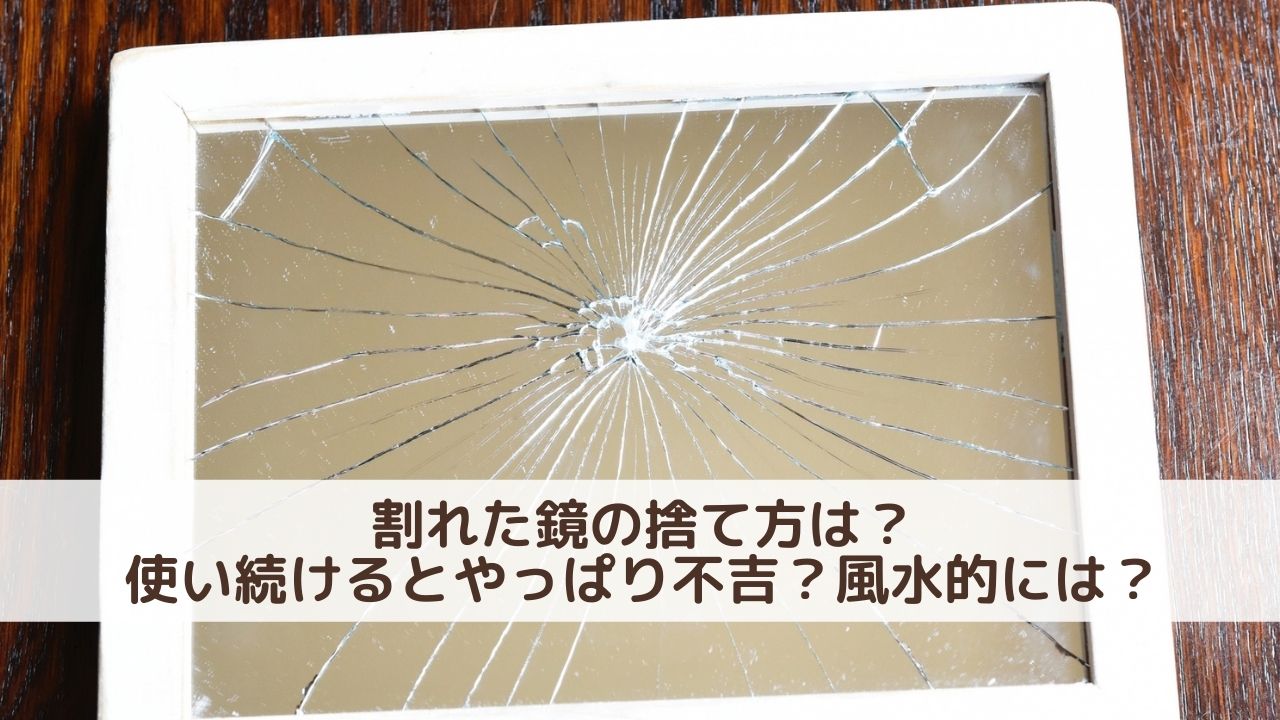




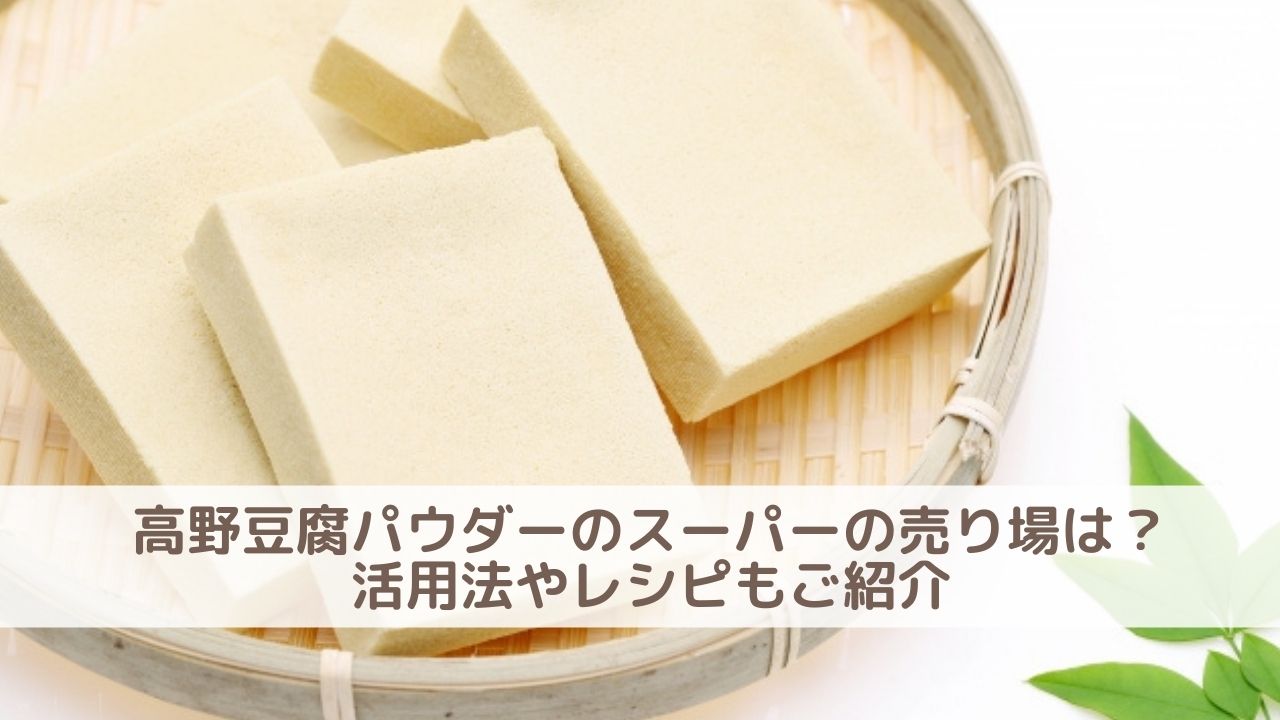





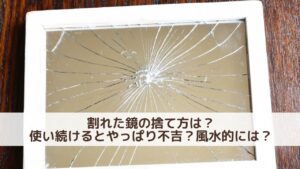



コメント